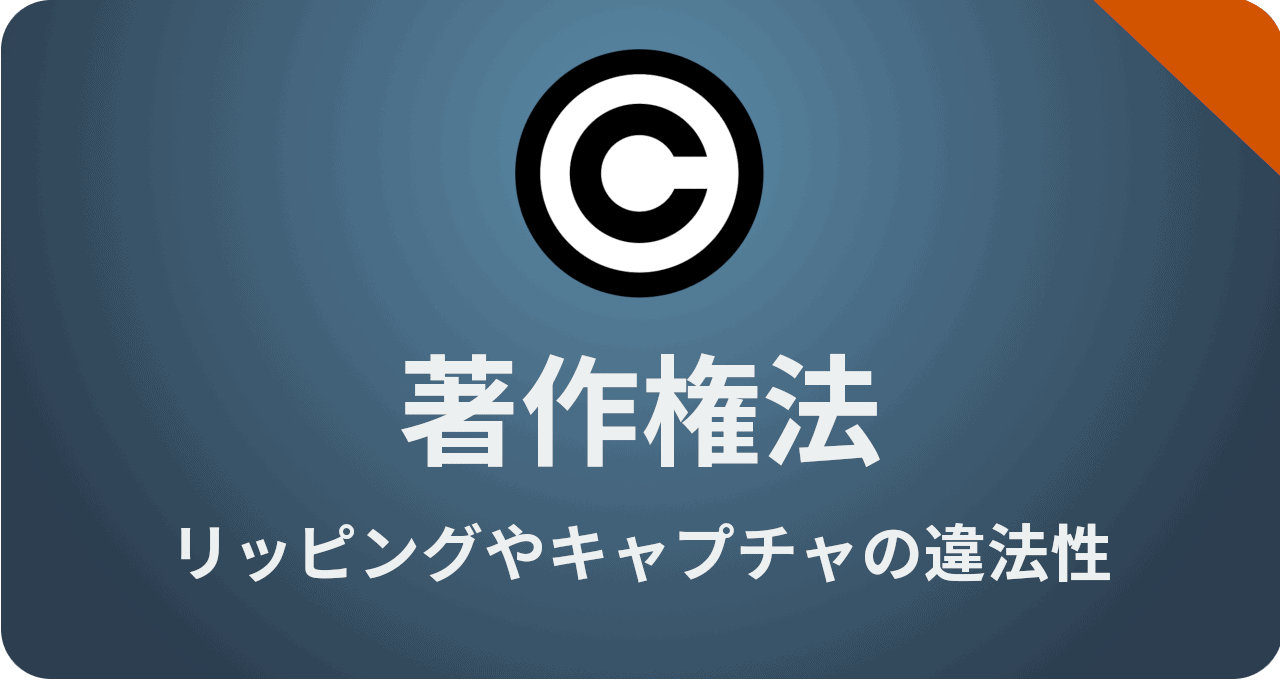著作権法は対象範囲が広く、どのような行為がどの条文に該当するかを把握するのは容易ではありません。しかし、たとえ悪意がなくても「知らなかった」では済まされないケースがあり、行為の内容によっては刑事罰や民事請求の対象となる可能性があります。
著作権法の基本と違法行為の分類
アプリを使用した行為で著作権法に抵触するもには、以下のような項目があります。
私的使用の複製 – 技術的保護手段の回避
著作権法では私的使用の複製を認めていますが、「技術的保護手段の回避」が禁止されているため、個人使用であっても、電子的方法や磁気的方法など人が知覚できない方法で保護されたコンテンツの複製は、著作権法に抵触します。
技術的保護手段は、DVD/ Blu-rayのコピーガードや、動画ストリーミングサービスなどの DRMが該当します。
著作権法 30条 2 項 – 私的使用のための複製の例外
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。) を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手 段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果 に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
⚠️コピーガードなど技術的保護手段を回避は、権利者の告訴がなければ起訴できない親告罪に該当し、刑事罰の対象にはなりません。
技術的保護手段の回避に関連する出来事
2012年10月に施行された改正著作権法により、技術的保護手段の回避を主な目的とする機器やプログラムの製造・販売・輸入・提供は、非親告罪として刑事罰の対象となりました。
これにより、たとえばマジコンや DVDFab、DVD Shrinkなど、コピーガードを回避する機能を備えたソフトウェアは、日本国内での提供自体が違法とされるようになりました。
リッピングアプリの違法性
リッピングアプリは、DVDやBlu-rayディスクの映像コンテンツを動画ファイルとして保存するためのツールですが、ディスクに技術的保護手段が施されていない場合に限り、私的使用の範囲でリッピングを行うことは著作権法上の問題とはなりません。
これは、著作権法が複製行為そのものではなく、コピーガードやDRMなどの技術的保護手段を回避して複製を可能にする行為を禁止しているためです。
DVDは、アクセスコントロール技術であるCSS(Content Scramble System)によって保護されています。CSSは実質的にコピーガードと同様の機能を果たしますが、2012年10月の法改正以前には、著作権法において「技術的保護手段」として明示的に定義されておらず、CSSの解除を伴うDVDリッピングの違法性には法的解釈の余地がありました。
しかし、著作権法の改正により、アクセスコントロール技術の回避を目的とする機器やプログラムの提供が非親告罪として禁止される対象となり、CSSで保護された DVDやゲームソフトのリッピングが著作権法違反として明確に違法と定義されました。
保護されている動画ダウンロードの違法性
動画配信サービスや音楽配信サービスでは、利用規約によってコンテンツの複製が禁止されていることが一般的です。
また、これらのサービスで配信されているコンテンツは、DRM(Digital Rights Management)と呼ばれる技術的保護手段によって保護されているため、コンテンツをダウンロードまたは録画・録音する行為は、著作権法上、技術的保護手段の回避に該当する違法行為になります。
画面録画(キャプチャ)について
画面録画(キャプチャ)による保存行為の違法性は、録画手段が技術的保護手段の回避に該当するかどうかが判断基準となります。
コンテンツ側で用いられている[DRM]や[暗号化方式]の保護技術と、録画ソフトに実装された[画面ミラーリング]や[APIフック]などの取得方法の組み合わせによって、著作権法上の評価が異なる可能性があるためです。
自炊本の違法性
個人が所有している書籍を自ら裁断・スキャンして電子化する「自炊」は、著作権法第30条に基づく私的使用の複製として合法です。
一方で、自炊代行業者が依頼を受けて他人の著作物をスキャンして電子化する行為は、私的使用の範囲を超えており、著作権者の複製権を侵害する行為と判断されます。
平成25年(ネ)第10089号 控訴審判決では、業者による書籍の電子化が「複製権の侵害」に該当するとされ、スキャン処理を含む自炊代行サービスに対して差止命令が認められました。
書籍の裁断(分解)のみを請け負う業者については、現時点では著作権侵害とまではされていません。そのため、裁断とスキャンを明確に分離し、分解のみを受託する形で営業している業者が多いのが現状です。
違法ダウンロード
2010年 1月 1日に施行の改正著作権法で、著作権を侵害している不正コピーされた[違法ファイル]のダウンロードが違法 になり、2012年 10月の法改正で罰則が適用されました。
2020年 6月に施行された改正著作権法で、違法ダウンロードの対象が音楽・映像だけでなく、静止画やテキストを含む著作物全般に拡大されました。
これには違法にアップロードされた漫画などを画面上に表示し、それをスクリーンショットとして保存する行為も含まれますが、社会生活上避けられない映り込みなど軽微なものは除外されます。
著作権法 30条 1項 3号
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
著作権法 30条 1項 4号
著作権(第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)
⚠️違法ファイルのダウンロードは、権利者の告訴がなければ起訴できない親告罪に該当します。
ただし、有償著作物(CD・DVD・書籍・有料配信など)について、違法にアップロードされたものであると知りながら、反復してダウンロードした場合は、刑事罰の対象となります。
この場合、著作権法第119条第3項により、二年以下の懲役、二百万円以下の罰金、またはその併科が科される可能性があります。
通信ログの保存と個人の特定
通常のインターネット接続では、ISP(インターネットサービスプロバイダ)の DNSを経由するため、ユーザーの接続ログがISP側に一定期間保存されています。
ブラウザの履歴やキャッシュを削除しても、ISPに記録されたIPアドレスや通信先ドメインの情報をもとに、法執行機関は特定のサイトへのアクセス履歴から個人を特定することが可能です。
通信の秘密とログ開示の制限
日本では、電気通信事業法 第4条第1項により「通信の秘密」が保障されており、通信内容や宛先は第三者に開示されません。
この秘密が侵害されるのは、本人の同意がある場合や、正当行為・正当防衛・緊急避難など、違法性が阻却される事由がある場合に限られます。
日本の電気通信制度は、先進国の中でもプライバシー保護の水準が高く、通信の秘密を厳格に守る仕組みとなっています。
一方で、SNSなどにおける誹謗中傷や違法行為の加害者を特定する際には、この制度が障壁となり、捜査や被害救済が困難になるケースもあります。
違法アップロード
著作権を侵害して複製したものを、ファイル共有ソフトや公開設定をしたオンラインストレージ、YouTubeなどの動画サイトにアップすると、著作権法 第23条の[公衆送信権を侵害]することになります。
著作権法 23条 – 公衆送信権等
一 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
二 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
⚠️著作物を権利者の許可なくアップロードする行為は、著作者が専有する公衆送信可能化権を侵害するものであり、著作権を故意に侵害した場合は、著作権法第119条により、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科が科される可能性があります。
また、これとは別に民事上の損害賠償請求を受けることもあります。
ファスト映画の賠償金
映画の内容を10分程度に再編集したファスト映画も、著作権者の許可なくアップロードすると「公衆送信可能化権」の侵害に該当します。
2021年6月には、ファスト映画を公開していた容疑者5名が摘発され、そのうち1人は和解金として1000万円を支払い示談が成立したと報じられました。
また、著作権法違反で有罪判決を受けた2人に対し、東京地方裁判所は著作権者側への損害賠償として総額5億円の支払いを命じています。

ファスト映画の公開に関与したとされるYouTubeチャンネルに対して、コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は、国際執行手続きを通じた特定作業を進めていると発表しています。
この手続きは、国外に拠点を置く違法アップロード者の実態解明を目的としたもので、法執行機関との連携により進行中です。
リーチサイト
2020年10月1日施行の改正著作権法により、違法ファイルへのアクセスを促す「リーチサイト」や専用アプリが新たに規制の対象となりました。
リーチサイトは、違法ファイルのダウンロード先リンク( Rapidgatorや Katfileなど)を集約・掲載し、利用者を侵害ファイルへ誘導するウェブサイトで、著作権侵害を助長する構造を持ちます。
第113条 2項(抜粋)
送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第1号に掲げるウェブサイト等(同項及び第119条第2項第4号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第2号に掲げるプログラム(次項及び同条第2項第5号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
改正法は、「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられること」と「殊更に誘導すること」の両要件を満たす場合に違法と規定しており、単発的なリンク掲載や情報紹介目的の記載は必ずしも規制対象とはなりません。
最終的な違法性の判断は個別事案に応じて司法が行うことになります。
⚠️リーチサイトの運営は、著作権法第113条第2項により「著作権侵害を助長する行為」として「みなし侵害」とされており、同法第119条第1項に基づいて、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその併科が科される刑事罰の対象となります。
法人が関与した場合は、著作権法第124条第1項により、3億円以下の罰金刑が適用される可能性があります。
起訴には原則として権利者の告訴が必要な親告罪ですが、悪質なケースでは摘発される事例も報告されています。
侵害ファイルの再配布構造
著作権を侵害するファイルは、インターネット上でさまざまな手段によって再配布されていますが、その構造には大きく2つの類型があります。
✏️2010年、秋田県の18歳の男子学生が、ファイル共有ソフトなどを通じて入手した漫画の違法ファイルを、海外のオンラインストレージサービス「Megaupload」にアップロードし、ダウンロード回数に応じた報酬プログラムを利用して約半年間で30万円の収益を得ていたと報道されています。
学生は 著作権侵害により書類送検されています。
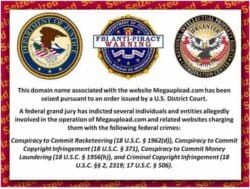
2012年、アメリカ司法省とFBIが主導する大規模な捜査により、海外のオンラインストレージサービス「Megaupload」が著作権侵害ほう助の疑いで封鎖されました。
この摘発以降、報酬制度を廃止するストレージ事業者が相次ぎましたが、現在もRapidgatorや Katfileなど一部のサービスではアフィリエイト制度が継続されており、マンガや映像作品などの違法ファイルがアップロード・共有される実態が確認されています。
非公開のオンラインストレージ利用の違法性
個人で私的使用の目的に複製した著作物であっても、DropboxやGoogle Driveなど、共有機能を備えたオンラインストレージに保存する場合、著作権法 第30条第1項第1号に定められた「自動複製機器」に該当する可能性があります。
著作権法 30条 2 項 – 私的使用のための複製の例外
一、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
⚠️「自動複製機器」とは、複製を行う者の意思によらず、自動的に複製を実行する機器やサービスを指し、これに該当すると判断された場合、非公開設定でアップロードした場合でも著作権法違反に問われる可能性があります。
携帯電話向け音楽サービス「MYUTA」は、ユーザー専用のオンラインストレージを用いて音楽データを保存・再生するサービスでしたが、一般的なオンラインストレージと異なり共有機能は存在していませんでした。
しかし、裁判所は「システムが事業者側でデータを複製・送信していた点」に着目し、個人による私的使用の範囲を超えるものと判断。音楽著作物の利用に関して、著作権者からの許諾が必要であるとの解釈が示されました。
このサービスは判決前にすでに終了していたため、差止請求は棄却されましたが、オンラインストレージへの著作物の保存が常に私的使用に該当するとは限らないことを示す事例とされています。
更新履歴
お問い合わせ
📬 ご質問・ご連絡は、メールか SNS(X または Bluesky)にて受け付けています。
原則として XではDMでのご連絡をお願いいたします。投稿への公開コメントでも対応可能ですが、内容により返信を控えさせていただく場合があります。
※ Blueskyには非公開メッセージ機能がないため、メンションによる公開投稿でのご連絡をお願いいたします。
- info[at]eizone[dot]info
- @eizone_info
-
@how-to-apps.bsky.social
※投稿内容に関するご質問には可能な範囲でお答えします。
ただし、当サイトはアプリの開発元ではなく、技術サポートや不具合の対応は行っておりません。
また、すべてのご質問への返信を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。